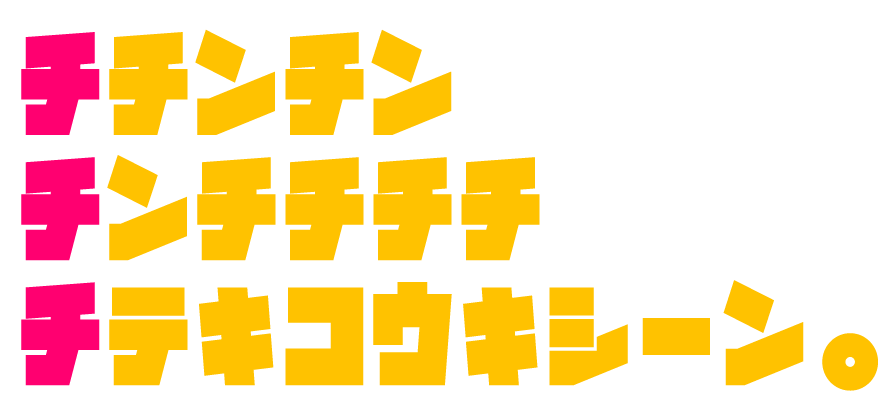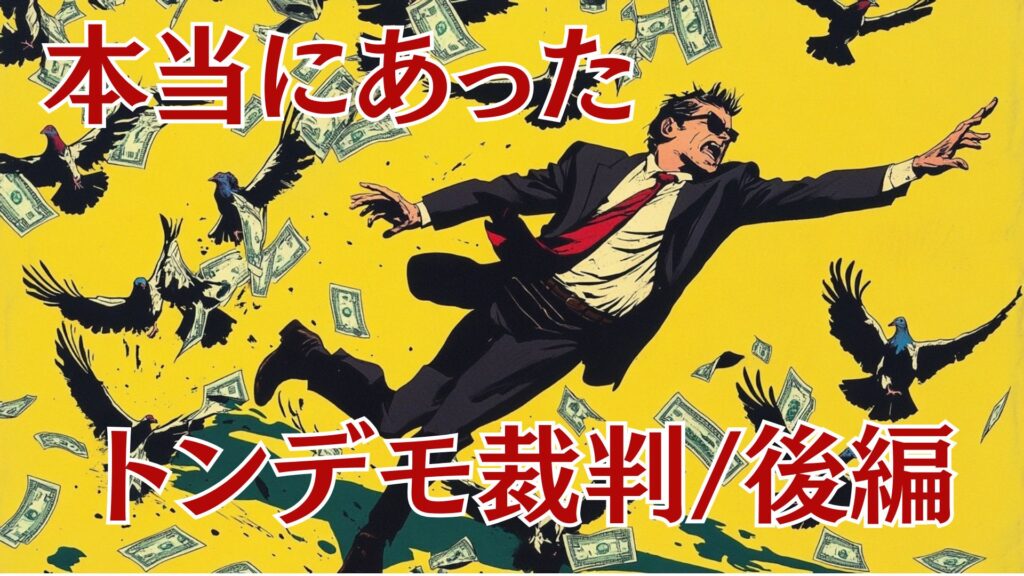
前編では、マクドナルドやレッドブルなど、有名企業にまつわる裁判をご紹介しました。続く後編では、「そんなことで裁判になるの!?」と驚くような、ユニークな裁判の数々をさらに深掘りしていきます。「Googleマップのせいで事故に遭った!」「就職できないのは大学のせいだ!」「鳩のフンで滑って転んだ!」など、思わず「えっ!?」と声に出してしまうような、驚きのエピソードが満載です。皆さんは、これらの裁判、どのような判決が下ったと思いますか?常識では考えられないような判決の数々に、驚愕すること間違いなしです!
Googleマップの案内を過信した女性の末路
歩道のない危険な道に案内され、車にはねられた女性の訴え
後編最初の裁判は、地図アプリ「Googleマップ」をめぐる、驚きの訴訟です。アメリカのユタ州に住む女性が、Googleマップで自宅までのルートを検索し、その案内に従って歩いていたところ、なんと、高速で車が行き交う、歩道のない危険な道に案内されてしまいました。そして、不幸なことに、女性は車にはねられてしまったのです。女性は、「Googleマップが危険な道を案内したせいだ」として、運転手とともに、Googleマップを訴えました。

危険性を警告する注意書きの存在と裁判の結果
一見、Googleマップの案内に問題があったようにも思えます。しかし、当時のGoogleマップには、「歩行者用ガイダンスはベータ版です。注意:このルートには歩道または歩道が欠けている可能性があります」という注意書きが表示されていました。つまり、Googleマップは、このルートが歩行者にとって危険である可能性を、事前に警告していたのです。裁判所は、この注意書きの存在を重視し、女性の訴えを退けました。「Googleマップよりも自分の目を信じてほしかった」という、裁判官のコメントが印象的です。
Googleマップの責任はどこまで?自らの判断の重要性
この裁判は、私たちに、地図アプリの便利な機能に頼りすぎる危険性を教えてくれます。確かに、Googleマップは非常に便利なツールですが、最終的に、その情報をもとに、どのような行動を取るかは、私たち自身の判断に委ねられています。夜間に、歩道のない、車が高速で行き交う道を歩くのは、誰が見ても危険です。この女性は、Googleマップの案内に頼りすぎて、自らの判断を怠ってしまったと言えるでしょう。
この裁判での争点は、主に下記の通りです。
- Googleマップの案内に従って歩いた場合、事故の責任は誰にあるのか?
- Googleマップに表示される注意書きの有効性は?
- 利用者は、Googleマップの情報と、自らの判断、どちらを優先すべきか?
この裁判から、googleマップなどの地図アプリは、あくまで参考程度にし、自分の目で見て、安全確認することが大切だと理解できますね。
大学に就職支援を求めた女性の驚くべき主張
就職活動の失敗を大学のせいにした女性の裁判
次にご紹介するのは、就職活動がうまくいかなかった女性が、なんと「大学が悪い」として、大学を訴えた裁判です。この女性は、ニューヨーク州の大学で情報工学の学位を取得し、卒業しました。しかし、卒業後の就職活動は難航し、なかなか就職先を見つけることができませんでした。女性は、「就職できないのは、大学の就職支援が不十分だったからだ」として、大学を訴えたのです。
大学側の対応と裁判所の判断
女性の主張は、「大学側は、正社員就職を支援すると言いながら、メールで数件の求人を紹介しただけだった」というものでした。女性は、大学が十分な就職支援を行わなかったために、自分が就職できなかったと主張し、学士号を取得するのに要した費用、約760万円の返還を求めました。さらに、「不毛に終わった3ヶ月の就職活動期間がもたらしたストレス」の代償として、約22万円の支払いを要求しました。しかし、大学側は、「このご時世で、就職を完全に保証してくれる大学などありはしない」と反論しました。裁判所も、大学側の主張を認め、女性の訴えを退けました。
就職活動における自己責任とは?
この裁判は、就職活動における「自己責任」の重要性を、改めて考えさせられる事例です。確かに、大学は学生の就職活動を支援する役割を担っています。しかし、最終的に就職先を見つけるのは、学生自身の責任です。大学は、あくまでも学生の就職活動を「支援」する立場であり、就職を「保証」する立場ではありません。この女性は、大学への依存心が強く、就職活動における自己責任を、十分に理解していなかったと言えるでしょう。
懲役中に自分を訴えた男の奇想天外な理論
懲役刑で市民権を侵害されたと主張した男の訴訟
続いては、「お前は本当に何を言ってるんだ」とツッコミたくなるような、奇想天外な裁判をご紹介します。1995年、アメリカのバージニア州で、ある男が、「自分自身を訴える」という、前代未聞の裁判を起こしました。この男は、酒に酔った状態で、重窃盗と押し込み強盗を犯し、23年間の懲役刑を言い渡されていました。男の主張は、「自分が犯した罪によって、自分が逮捕され、懲役刑を受けることになった。その結果、自分の自由が奪われ、市民権が侵害された。これは、自分自身が悪いのだから、自分自身に対して、約5億4000万円の損害賠償を請求する」というものでした。
訴訟の真の目的と裁判所の反応
この突拍子もない主張、皆さんは、どのような意図があると思いますか?実は、この男には、ある狙いがありました。男は、「自分は服役中で支払い能力がない。だから、自分を管理している州が、代わりに損害賠償金を支払うべきだ」と主張したのです。つまり、この男は、州から約5億4000万円を、タダで手に入れようと企んでいたのです。しかし、当然ながら、裁判所は、この男の訴えを、すぐに却下しました。
刑務所内からの奇策
この裁判は、常識では考えられないような、珍しい事例です。しかし、この男のように、刑務所の中から、あの手この手で、金儲けを企む受刑者は、少なくありません。この男の試みは失敗に終わりましたが、この一件は、私たちに、人間の持つ、ある種の「したたかさ」を、垣間見せてくれる、興味深い事例と言えるでしょう。
鳩の糞で転倒、7億円請求した男性の勝訴劇
駅構内の鳩の糞で転倒し、多額の賠償金を求めた裁判
次は、なんと「鳩のフン」をめぐる裁判です。ニューヨークの地下鉄駅構内で、ある男性が、階段に落ちていた鳩のフンを踏んで滑って転倒し、怪我を負いました。男性は、「鳩のフンをきちんと清掃していなかった、交通当局の怠慢だ」として、交通当局を相手取り、約7億円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

交通当局の過失と男性への賠償命令
「鳩のフンで滑って転んだ」と聞くと、「それは運が悪かったね」と思う方も多いでしょう。しかし、この裁判、なんと、男性側が勝訴したのです。裁判所は、交通当局に対して、約8億8000万円の支払いを命じました。ただし、男性自身にも、鳩のフンを避けられなかった過失があるとして、20%の過失を認め、交通当局には、賠償総額の80%、つまり約7億円の支払いを命じました。
鳩の糞問題、責任の所在はどこに?
この裁判では、男性が、出勤時に階段に鳩のフンがあることを確認し、帰宅時にも、まだ鳩のフンが放置されていた、という点が、重要なポイントとなりました。つまり、交通当局は、鳩のフンの存在を認識していながら、適切な清掃を怠った、と判断されたのです。この判決は、公共の場における、安全管理責任の重要性を、改めて示すものと言えるでしょう。
この裁判での争点は、主に下記の通りです。
- 駅構内の鳩のフンは、誰が責任を持って清掃すべきか?
- 鳩のフンによる転倒事故は、どの程度予見可能か?
- 利用者は、駅構内の鳩のフンを、どの程度注意して避けるべきか?
女子高生との関係は淫行か純愛か? 争われた裁判の行方
既婚男性と女子高生の関係をめぐる裁判
ここからは、日本の裁判事例を見ていきましょう。まずは、愛知県で起こった、ある既婚男性と女子高生の関係をめぐる裁判です。この男性は、当時、妻と子供がいるにもかかわらず、17歳の女子高生と、いわゆる「不倫」の関係にありました。そして、男性は、女子高生と淫行をしたとして、愛知県の青少年保護条例違反の罪に問われました。
純愛ゆえの行為か、性的欲求に基づく行為かの判断
この裁判の争点は、「二人の関係が、淫行なのか、それとも純愛なのか」という点でした。青少年保護育成条例は、未成年者を性的な対象として扱う行為を禁じています。しかし、純愛に基づく交際までを、罰することはできません。つまり、二人の関係が、「純愛」なのか、それとも、男性の「性的欲求を満たすための行為」だったのか、という点が、この裁判の、重要なポイントとなったのです。
裁判結果と不倫問題への波紋
裁判では、二人がホテルでの行為以外にも、ドライブデートをしたり、映画を見に行ったりしていたこと、そして、お互いに「愛し合っている」と認識していたことが、明らかになりました。その結果、裁判所は、「二人の行為を、淫行と断定するには、疑問が残る」として、男性に無罪判決を下しました。つまり、二人の関係は、「純愛」であると認められたのです。しかし、この判決は、大きな波紋を呼びました。なぜなら、男性は、妻子ある身でありながら、未成年の女子高生と、不倫関係にあったからです。「純愛」という名目で、不倫や未成年者との性行為を、正当化して良いのか、この裁判は、私たちに、難しい問題を突きつけています。
この裁判で争われた主な項目は下記の通りです。
- 男性と女子高生の関係は「淫行」か「純愛」か?
- 青少年保護育成条例における「淫行」の定義とは?
- 既婚者と未成年者の交際は、どのように判断されるべきか?
「殴れるもんなら殴ってみろ」 挑発と暴行の境界線
挑発に乗って暴行した男性の裁判
最後にご紹介するのは、「殴れるもんなら殴ってみろ」という、挑発的な言葉をめぐる裁判です。2008年、宮崎県で、二人の男性が口論になりました。よくある酔っ払いの喧嘩です。しかし、次第に、二人の口論はエスカレートし、一方の男性が、相手を挑発し始めました。「殴れるもんなら殴ってみろ」と。すると、挑発された男性は、この言葉に乗り、相手の男性の顔を数回殴ってしまったのです。殴られた男性は、警察に通報し、傷害事件となりました。
被害者の同意と暴行罪の成立
裁判では、「殴った男性が、暴行について、被害者の同意があった」と主張し、無罪を主張しました。「殴ってみろ」と言われたのだから、殴っても問題ない、という理屈です。しかし、裁判所は、「殴ってみろという言葉は、口論中の、あくまでも挑発的な言葉であり、暴行を受ける承諾とは言えない」と判断し、殴った男性に、罰金25万円の支払いを命じました。
挑発と承諾の微妙な関係
この裁判は、言葉による「挑発」と、暴力に対する「承諾」の、微妙な関係性を、私たちに考えさせる事例です。「殴ってみろ」という言葉は、本当に、相手に殴ってほしい、という意味で、発せられたのでしょうか?おそらく、そうではないでしょう。しかし、言葉を受け取った側は、その言葉を、文字通りに受け取り、暴力に訴えてしまったのです。この裁判は、言葉の持つ力、そして、言葉の解釈の難しさを、改めて、私たちに教えてくれています。
この裁判での争点は、主に下記の通りです。
- 「殴ってみろ」という言葉は、暴行に対する「承諾」とみなせるか?
- 口論中の挑発的な言葉は、どの程度、法的に考慮されるべきか?
- 暴行罪の成立における、「被害者の同意」の有無は、どのように判断されるべきか?
まとめ:世界の珍裁判に見る人間の行動と責任の曖昧さ
今回、ご紹介した裁判事例は、どれも、人間の行動と、それに伴う責任の、曖昧さを、浮き彫りにするものばかりでした。私たちは、日々、様々な判断を下しながら、生活しています。しかし、その判断が、常に正しいとは限りません。また、自分の行動が、どのような結果を招くか、完全に予測することも、不可能です。今回、ご紹介した裁判事例は、私たちに、人間の行動と、それに伴う責任について、改めて、考えさせる、貴重な機会を与えてくれていると言えるでしょう。
前編、後編を通して、世界中で実際に起こった、驚きの裁判事例の数々をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?これらの裁判から得られる教訓は、私たち自身の、日々の生活にも、きっと役立つはずです。皆さんも、今回の記事を参考に、身の回りの出来事について、少し違った視点から、考えてみてはいかがでしょうか?それでは、また次回の記事でお会いしましょう!